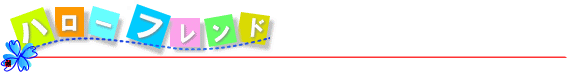

皆さんは、最近ベストセラーになっている 『大往生したけりゃ医療とかかわるな 「自然死」 のすすめ』 をご存知でしょうか。
衝撃的なタイトルですが、現役医師が毒舌とユーモアを織り交ぜながら、現代医療のあり方に痛快なメスを入れています。スタッフ全員が絶賛し、身近な人に薦めています。そこで今回は、この本の紹介を兼ねて感じたことを少し述べてみたいと思います。

平成20年の厚生労働省の調査によると、「延命治療を中止して、自然に死期を迎えること」 を希望する人は全体の約3割で、10年前の2倍に増えているそうです。皆さんの中にも、「死にゆく老人に対して過剰なまでの医療がはたして必要なのか?」 と、疑問を抱いている方がいらっしゃるのではないでしょうか。この本はそうした疑問に対して、明確な答えを示してくれています。
著者は、特別養護老人ホーム 「同和園」 の常勤医師をされている “中村仁一” 氏です。これまでガン患者を含めて多くの老人が安らかに “自然死” するのを看取ってきました。その経験から、現代医療がかえって患者の “穏やかな死” を邪魔している現状を紹介し、「自然死こそ、本来あるべき安らかな死である」 と提言しています。
現代医療の間違いや日本人の医療に対する思い込みや “死“ についてなど、暗くなりがちなテーマを明るく軽快なタッチで述べています。「そうそう」 と納得したり、「目からウロコ」 といった内容や思わず吹き出してしまう笑い話もあり、あっという間に読めてしまいます。そして最後には、きっと “死” に対する恐怖心がなくなり、身内や自分の死をどう迎えるべきか、正しい方向を見いだすことができるものと思います。皆さんにも、ぜひお薦めしたい一冊です。
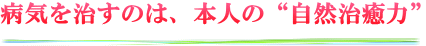
中村氏は初めに、ご自身が考案した 「治療に関する思い込み度テスト(15の項目からなる)」 を紹介し、日本人がいかに医療に期待しているかを説いています。例えば、①ちょっと具合が悪くなると、すぐに医者にかかる ②薬を飲まないことには病気はよくならない ③病名がつかないと不安……など、誰もが思い当たることばかりです。
私たちの子供の頃は、病院が少なかったこともあり、多少のことでは医者に掛からないのが普通でした。しかし今では、「少し具合が悪くなれば病院に行って薬をもらう」 というのが当たり前になっています。病院はお年寄りであふれ、たくさんの薬袋を抱えている人をよく見かけます。健康保険制度のお蔭で、誰もが気軽に病院に行けるようになったことはとても素晴らしいことですが、それにしても医者や薬に頼りきっている人が多過ぎるように思います。
そうした現状に対して、中村氏はきっぱりと 「今の日本人は、医療に対して期待を抱きすぎです。病気を治す力の中心をなすものは本人の “自然治癒力”、 医者でも薬でもありません。医療者はお助けマン、薬はお助け物質、器械はお助けマシーンです。元来、化学物質である薬は異物であり、身体にいいもの、必要なものではありません」 と述べています。
私たちも、これにはまったく同感です。現代西洋医学は患者の症状だけを問題としているため、それを取り除くための治療や薬が施されます。ただの風邪でも風邪薬・解熱剤・抗生物質・胃薬……と何種類もの薬が処方されます。しかし発熱や咳などの症状は、治癒に向けての身体の正常な反応ですから、よほどの重症でないかぎり休養をとっていれば自然と治ります。薬で抑えることで、かえって “自然治癒力” の働きを阻害することになってしまいます。

私たちは、よほどのことがないかぎり病院には行きませんし、薬もなるべく飲まないようにしています。薬依存や薬漬けの医療が薬の弊害を生み、健康レベルの低い人間をますます増やしているように思えてなりません。中村氏のような医師が増え、日本人が医療に対する考え方を根本から改めないかぎり、健康な長寿社会は築けないのではないでしょうか。

多くの老人は病院や老人施設で死を迎えています。自宅で静かに息を引きとる人が本当に少なくなっていますから “自然死” といってもピンとこない方が多いのではないかと思いますが、“自然死” とはいわゆる老衰死、餓死のことです。餓死と聞くと、とても悲惨な状況を想像されるかと思いますが、死期が近づけば誰でも食べられなくなるのが 「自然の摂理」 です。そうした人が医療措置を何も受けずに迎えるのが “自然死” です。昔の人は皆、こうして死んでいきました。中村氏は 「死に際にはどんな人間も脳内にモルヒネ様物質が分泌され、痛みや苦しみがなく、まどろみのうちに安らかに死んでいく」 といいます。そういえば、臨死体験をした人の話の中にも 「とてもいい気持ちだった」 とありますから、“死” は決して苦しいものでも苛酷なものでもないようです。
しかし今の医療現場では、そう簡単には死なせてもらえないのが現状。食べられなくなれば、鼻からのチューブ栄養や胃ろう (お腹に穴をあけてチューブ栄養)・点滴注射が行われ、他にも酸素吸入や輸血などの処置が当然のごとくなされます。“死の先延ばし” が医者の使命であるかのごとく考えられています。死と向き合う医者でありながら、「ほとんどの医者は自然死を知らないし、人間が自然に死んでいく姿を見たことがない」 という指摘には、本当に驚きです。一方、患者側も 「できるだけの手を尽くしてあげたい」 と願う家族や、医療措置を行わないことがまるで愛情の欠如であるかのような風潮がありますから、死ぬに死ねない状況が繰り返されているわけです。中村氏はそうした医療を 「せっかく自然が用意してくれている安らかな死をぶち壊した “拷問” にも似た行為である。辛くても死ぬべき時期にきちんと死なせてやるのが “家族の愛情” である」 と述べています。

私たちも本当にそう思います。“自然死” こそ、「自然の摂理」 にかなった人間らしい安らかな死に方だと思っています。大半の人は 「死は最大の不幸」 と考えていますから、愛する家族には少しでも長く生きていてほしいと願います。しかし私たちは 「死は不幸なことではなく、精いっぱい生きたご褒美である」 と考えていますので、親や家族は 「すんなりと死なせてあげたい」 と思いますし、自分の死に対しても自然死を望んでいます。それが、人間を 「霊を含めたトータル的存在」 と見なす “本物のホリスティック医学” のあり方であると考えます。
フランスでは 「老人医療の基本は、本人が自力で食事を嚥下できなくなったら、医師の仕事はその時点で終わり、あとは牧師の仕事です」 といわれているそうです。日本の医療がいかに “唯物主義” に基づいているか、また信仰心のない国民性が今の医療を生み出しているかがわかります。医療従事者はもちろんのこと、日本人一人一人が正しい “死生観・死後観” を持たないかぎり、「死 = 最大の悲劇 ・医学の敗北 → 少しでも患者を生き永らえさせる医療」 こうした構図は改善されないのではないでしょうか。

これから何十年か先には、間違いなく老人ばかりの “超高齢化社会” が訪れます。そのときには多くの老人が病院にも施設にも入れず、家族が自宅で看取らなければならない状況が起こってくるでしょう。否応なく、“自然死” が求められるようになるものと思います。この本は、そうした時代に向けての先駆けのような気がします。同時に 「日本人がどのように生き、どのように医療と関わり、“死” と向き合っていくか」 という、人間にとってのきわめて深い問題を提起しています。
この本がきっかけとなり、終末医療が少しでも改善され、自然の摂理にそって安らかにあの世に行く老人が増えていくことを心から願っています。

PS: 私たちが思わず笑ってしまった中村氏のエピソードを一つ紹介します。
「昔は、お腹の中に回虫やサナダムシがいる人がたくさんいました。こうした人が死にかけると、虫たちがいち早く察知して 『こんなところにいたら、いのちがなくなる』 と、口や肛門から脱出。それを見た一族の長老が 『とうとう虫にも見離されたか』 と、もう長くはないことを告げます。これを “専門用語” で 『虫の知らせ』 といったとか……」