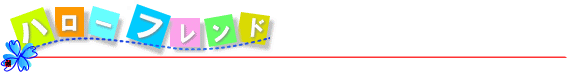

今年の、アカデミー賞最優秀外国語映画賞を見事受賞して、話題になった『おくりびと』は、納棺師という職業を通して日本独特の死生観をあらわしています。この映画によって、日本人のもつ深い精神世界を、世界中の人々に示すことになりました。海外からの高い評価を獲得できたのは、日本人の“心”に世界の人々が共感したということではないでしょうか。
英題がDepartures(出発・門出)というのは、「死は終わりではなくあの世への旅立ち」という意味から。その通過点となる遺族との別れのとき、死者が旅立つための身なりをきちんと整えて送りだすのが、“納棺師”=“おくりびと”の仕事です。
“おくりびと”が、まるでお茶の作法のような美しい所作で、心をこめて務める姿からは、納棺が神聖な儀式であることが伝わってきます。
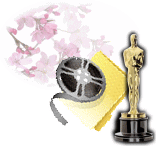
“もっくん”こと本木雅弘さんが主演したこの映画は、彼が15年前にインドを放浪した経験や、『納棺夫日記』という本にめぐりあったことなどがきっかけとなり、自ら発案した企画だそうです。“もっくん”は、年を経る毎に味があって深みのある俳優さんに成長されていますね。協力者を徐々に得ながら企画を具体的に実現させたその執念と、内面性の深さが実ったようで、この映画はアカデミー賞のほかにも日本や海外で数々の賞を受賞しています。
ところで、“納棺師”のことでふと思い出した話があります。今から30数年前、スタッフが知人から聞いた本当にあった話です。それはある家庭でのお通夜のできごとでした。
お通夜前の納棺のひととき、そのお宅では“納棺師”ではなく身内によって、故人に旅立ちのための身支度を整えていました。経帷子(きょうかたびら)とよばれる白い着物、手甲、脚絆(きゃはん)、白足袋、わらじ・・・と順に着けていき、あとは三角の頭巾(怪談で幽霊が額につけている三角の布)を残すばかりとなりました。
そしてお坊さんを迎えお通夜を始めようとしたその時、お坊さんは、まだ故人の横に置いてある三角頭巾に気づき、「つけてください」と喪主に言いました。喪主はいかにもまじめそうな若いお父さんで、喪主という大役はもちろん初めての体験です。そのうえ、葬儀に出席した経験も、あまりなかったようです。
お坊さんから急(せ)かされたように感じたお父さんは、急いで三角頭巾を手に取りました。ところが次の瞬間、こともあろうにそれをそのまま自分の額につけてしまったのです。いくら喪主が初めての体験とはいえ、大まじめに額に三角頭巾をつけているお父さんの、あまりにもすっとんきょうな姿に、親族でさえ、さすがに声をかけることができません。
するとそれを見たお坊さん、顔色ひとつ変えることなく、「それは、お御霊(みたま)に」とサラリとおっしゃったのです。そのひと言で、三角頭巾は無事ご遺体の額に納まり、滞りなく納棺とお通夜を済ませることができました。本来ならしんみりと故人を偲ぶはずのお通夜が、その一件で“泣くに泣けない通夜”になったことは言うまでもありません。

映画『おくりびと』が、このお通夜のできごとを思い出させ、久しぶりにスタッフ揃って大笑いしてしまいました。